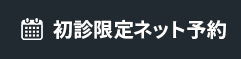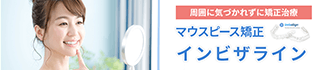私たちの歯は日々さまざまな刺激を受けています。その中でも、意外と知られていないのが「酸蝕症(さんしょくしょう)」です。
酸蝕症とは、酸によって歯の表面(エナメル質)が溶けてしまう状態のこと。虫歯や歯周病とは異なり、細菌の影響ではなく、食べ物や飲み物の酸が直接歯を溶かしてしまうのが特徴です。
そこで今回は、酸蝕症の原因や予防法についてご紹介します。
酸蝕症の原因とは?
酸蝕症の主な原因は、日常的に口にする酸性の食品や飲み物です。以下のようなものが歯に影響を与える可能性があります。
酸性の飲み物:炭酸飲料やスポーツドリンク、ワイン、柑橘系の果汁ジュースなど。
酸性の食品:柑橘類、ドレッシング、ピクルスといった酢を使った食品など
生活習慣や疾患による影響:逆流性食道炎や頻繁な嘔吐で胃酸が口の中に上がってくるなど
酸蝕症の症状
酸蝕症が進行すると、以下のような症状が現れることがあります。
- 歯がしみる(知覚過敏)
- 歯が黄白濁したり色っぽく見える
- 歯の先端が丸くなるなど形が変わる
- 歯が弱くなりかけやすくなる
- 虫歯の様な痛みが出る など
初期の段階では自覚症状が少ないため、気づいたときには進行していることもあります。
酸蝕症の予防方法
- 酸性の飲食物を控える
- ダラダラ飲み・食べをしない
- バランスの良い食事を心がける
- よく噛んで食べたり、唾液腺マッサージで唾液の分泌を促す
- 酸性の飲食物を口にした直後は歯の表面が柔らかくなっているので、まずはうがいをして、歯磨きは30分~1時間ほどあけてから行う
- 酸蝕症の初期は気が付きにくいため、定期的に歯科医院でチェックを受ける
- フッ素配合の歯磨き粉や洗口液を取り入れる
まとめ
今回は、酸蝕症の原因や予防法についてご紹介しました。
酸蝕症は、普段の食生活や生活習慣の影響で起こるため、誰にでも起こりうる症状です。しかし、適切な予防とケアを行えば、進行を防ぐことができます。
歯を守るためには、毎日の小さな習慣がとても大切です。自分の歯を大切にし、一生健康な歯を保ちましょう!